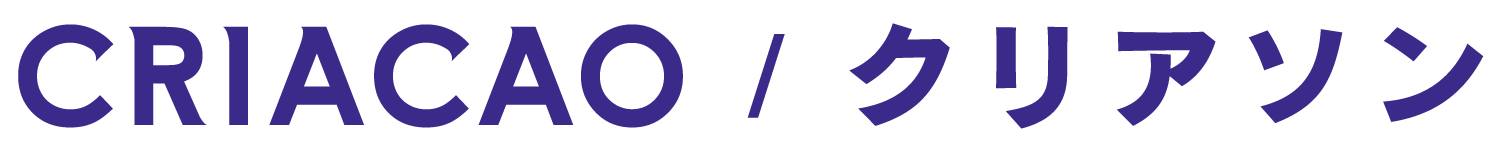PROFILE

成山 一郎
Criacao Shinjuku 監督
2007年 - 2009年:関西学院大学体育会サッカー部 ヘッドコーチ
2010年 - 2016年:関西学院大学体育会サッカー部 監督
2017年 - 2018年:愛媛FC トップチームコーチ
2018年 - :株式会社Criacao/Criacao Shinjuku 監督
選手とは、人と人としての付き合いをしたい
監督というと上下関係を意識されて、選手からは一線引かれて見られがちですが、できる限り、人と人として付き合いたい。ガチガチにならずコミュニケーションしていきたいと思っています。
大きな目標に向けて、良い仲間と一歩一歩向かっていく、個人としても成長していく、そのプロセス自体が幸せなことであり、価値あることだと思っています。
関西学院大学の大先輩である長沼健さんの言葉に、
勝利への道の探索が、そのまま人間性の追及につながっていることをいつまでも信じていたいと思う
とあります。
私はこの言葉を見たときに大きな衝撃を受け、以来、サッカー人生の指針としてきました。
勝利と人間性の「両立」というよりも、お互いにもっと「統合された何か」ではないかと思うのです。スポーツというものは、無我夢中で打ち込んで結果につながり、振り返れば人間的にも成長できていたというのは、私自身の実体験でもあるし、選手たちもそうではないでしょうか。
これはそのまま、クリアソンの理念につながるものではないかと思うのです。
前に、速く、何度でも

クリアソンのサッカーで大切にしていることを一言で表すと、「前に、速く、何度でも」です。
クリアソンに来て、練習初日の雰囲気を見て感じたのが、本気で世界一を目指しているということ。「できるわけがないとバカにされても、気にせず前に進むんだ」とみんなが思っていて、それがピッチ上でもすごく表現されていました。
サッカーも一緒です。点を取るために、前にある相手ゴールを目指し、自チームのゴールから相手を遠ざけるためにも前に処理したほうがいい。「前に」はクリアソンのサッカーにとって極めて重要な要素です。
「速く」について。昨今は選手のレベルや速さ、強度が向上しています。以前のカテゴリーでは自分がボールを持ったときに周りを見る余裕がありましたが、いまはボールをもらった瞬間に一気に寄せられるので、それを上回るスピードで自分たちのプレーをしなければ、ゴールに迫れず点が取れません。高いレベルでのサッカーで勝利するために「速さ」は不可欠です。
「何度でも」は、まさにクリアソンの精神を表したものです。世界一を本気で目指していて、当然くじけそうなときも何度もありますが、100回くじけても101回起き上がればいい。実際にプレー中も「ごたごた文句言わずに次のプレーをやるぞ!」、という声がかかりますが、ワンプレーごとに下を向いているようではダメ。常に、何度でも次に向かえる姿勢こそ大事なのです。
極限で何ができるかが、そのチームや選手の実力
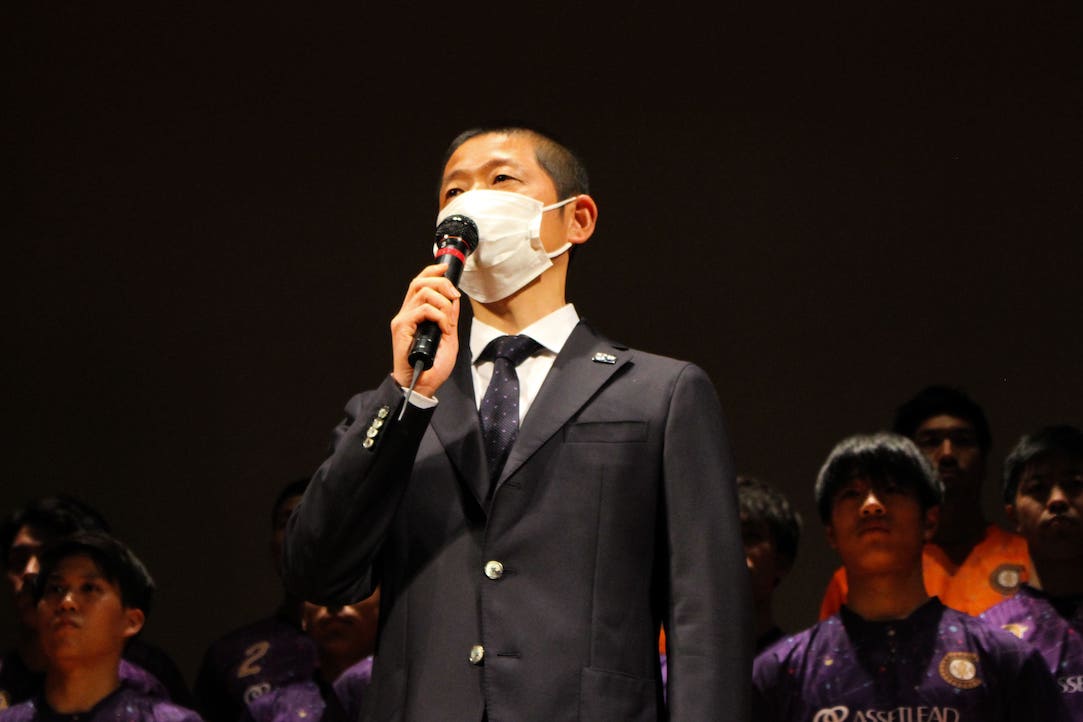
関西学院大学のアメフト部はスポーツチームの中で日本一の勝率を出しているのだそうです。そのヘッドコーチに勝つための秘訣を聞きに行ったところ、
極限で何ができるかが、そのチームや選手の実力だ
と教えられました。
優勝などの目標に向かっているときは同等かそれ以上に強い相手がいます。人生がかかったような試合などでプレッシャーが半端ではないときには、思うように行かないことが半分以上です。そのときにそのチーム、その選手に何ができるのかが真の実力なのだということでした。
自分たちのチームを見てみると、やはりうまく行かないときにそのチーム、その選手の本質が見えるものだと分かりました。暴言を吐いたり、人のせいにして下を向いてしまうと、途端にパワーがなくなるものなのです。
相手が強すぎると感じたり、味方が思うように動いてくれなかったり。審判も思うように吹いてくれない。イエローカードの累積で10人になってしまった。監督の私からしても、予定していた選手が怪我をしてしまうなど、スポーツやサッカーは思い通りに行かないことばかりです。だからこそ、「前に、早く、何度でも」の精神で極限の場面にも強いチームでありたいのです。
戦術、プレーモデル、そして選手たちのプレー
.jpg)
サッカーは、コミュニケーションし、判断し、目に見えるプレーとして表現しているものです。ピッチ上でボールを通じて味方と情報を受け渡しすることで、相手チームの選手がどこにいるのか、面と向かっている選手がどんな能力の持ち主なのかも含めた情報処理、情報交換を瞬時に行うスポーツです。そして、コミュニケーションを通じて判断したことを実行するのがプレーです。
「判断」と「プレー」とを合わせるのに必要なのが戦術、「プレーモデル」です。「こちらがボールを保持している攻撃時」、「相手にボールを保持されている守備時」、そして、「守備から攻撃への切り替え時」、「攻撃から守備への切り替え時」これら4つの局面に分けて、その対応を考えるのが今のサッカーの主流です。私はその4つの局面を、さらに「3つの状態」に分けています。たとえば攻撃時なら自陣でボールを持っているとき、相手ゴールに迫りつつあるとき、ゴール前でシュートを狙うときという3つに分けるので、全部で12分類になります。そのそれぞれにおいて、判断するための原則的な考え方をチームとして決めており、それをプレーモデルと呼んでいます。
いま、情報はいくらでも取れる時代です。サッカー自体に原理原則もあるので、どのチームでもサッカーが同質化しがちです。その中で、クリアソン独自のサッカーである「前に、速く、何度でも」を実践するために、どう攻撃や攻守切り替えをするのか、どう処理するのか、といったプレーモデルを軸として持っています。
監督としてメンバーをどう選ぶか
連勝に連勝を重ねてJFLに昇格した2021年シーズンのことです。元Jリーガーがそろったスタメン表Aでいかずに、サークル出身者も多く混じったスタメン表Bで臨んだ試合がありました。その時には何人かに説明を求められました。私はこう答えたのです。
Aのメンバーの能力を100だとすると、Bのメンバーは全力を出しても70の能力しかない。
しかし、Aは驕りが出たりすると90や80になってしまう。それでもBよりは高いだろう。歴代見てきたクリアソンらしい選手たちは、70だろうが50だろうが全部を出し切る。それが「戦う、走る、声を出す」というクリアソンのスタイルに凝縮されている。それができるのが自分たちの代表であるスタメンなのだ。
パートナーも観客も、それが観たくてクリアソンを応援してくれているのだと思います。ですから、どんなキャリアの選手であろうと、100%を出し切らないのであれば、それはダメだということです。

理念への共感と、その体現を何より大切にしたい
全力を尽くさないのは、ゲームにも人生にも良くない。クリアソンがサッカーをやる理由を定義すると、サッカーで勝って喜ぶためではなく、理念の体現のためであって、そこが他のチームとの決定的な違いなんです。私もそのつもりで監督をやっています。だからこそ、批判されても、勇気ある決断をするときがあります。クリアソンの選手たちが大切にしているのは、自分たちのサッカーで感動を与え、その人たちの生きる力になりたいという想いに尽きるのです。
「どうやるか」は選手たちのもの
戦術は監督が提示できますが、クリアソンの目指す世界一の経験者や答を持っている人はいません。何が正解か分からないのを、少しずつ前へ前へとみなで進んで、やっとここまで来たという感覚です。 ですから監督として、「何をやるか」は伝えられますが、「どうやるか」は選手1人1人が考えることだと尊重しています。自分を信じて、主体性を発揮して、自分たちのサッカーを創っていこうとできる人こそがクリアソンにフィットすると思います。
みんなで一つの生命体
関東1部リーグで5位に終わった年がありました。2020年のことです。不完全燃焼のシーズンに思えたのですが、最後に臨んだカップ戦の決勝の様子が強く脳裏に刻まれています。
チームが1つの生き物に見えて、そのなかで1人1人がキラキラ輝いて、個性も発揮されていて、これはすごいチームだと本当に感動しました。生命科学の世界に「二重生命」という言葉があります。生物の身体は、細胞や臓器が全体に向けて1つ1つが貢献して機能しているということ。自分の持ち場を守って、強みを発揮するというのが、命をみたときに大事な考え方だということです。この決勝戦はまさにそれを表していて、チームのために各人がそれぞれの個性を全力で発揮しているのがつながって、1つに見えました。
これは、クリアソンとサッカー界、クリアソンと世の中全体との間にもあるはずです。もちろん、会社としてのクリアソンやそこでの仕事にもいえることです。この感覚は、クリアソンでサッカーをやるときに大事です。仲間・相手・審判に影響を受け、アフターコロナで有観客でもパワーをもらい、改めて感じた、観客やパートナー、新宿という地域の力があります。このつながりこそが、クリアソンの理念に通じるのです。だからこそ、全力でサッカーをやる。そこに価値がある。クリアソンは、そういうチームです。
ご興味をお持ちいただけたら、ぜひ一度お話しましょう。